 |
| [[一般サイト>プラスチックプラス>エコロジー・農業用プラスチックフィルムの再生利用]] |
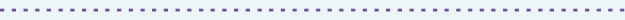
| 農業用プラスチックフィルムの再生利用 |

|
ビニルハウス・トンネル・マルチ栽培で野菜などを生産していますが、ここで被覆資材などに大量の農業用プラスチックが使用され、大量のプラスチックが排出しています。
農林水産省の統計では、1997年には17万8千トンに達しています。そのうち農業用塩化ビニルフィルム(農ビ)が59%、農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ)が37%、その他のプラスチックフィルムが3%、寒冷紗・育苗箱ポット・肥料袋などが2%となっており、ほとんどがプラスチックフィルムを占めています。
同年の農業用プラスチックフィルムの処理は再生利用が28%、埋め立て処理が24%、焼却処理が35%、その他の処理が13%となっています。
その内容は材質によって大きく異なり、農ビフィルムは比較的再生しやすいので再生処理が45%と多く、埋め立て26%、焼却15%となっています。いっぽう、農ポリフィルムは再生処理4%、埋め立て21%、焼却66%と多くなっています。
1970年代、環境上の問題指摘され、国(農林水産省)が対策に取り組み、野焼きを禁止するとともに、県、市町村、農業団体、関係団体(日本施設園芸協会・日本ビニル工業など)が協力して回収、リサイクルの促進をはかり、高知県・山梨県・茨城県・群馬県に公的施設ができ、民間企業も加わって主に農ビフィルムの再生処理が進んでいます。
最近さらに新たな再生原料の用途先の開発を進めてリサイクルを拡張するとともに、適正な処理がおこなえる体制の早急な設備を急いでいる。
使用済みとなった農ビフィルムは各農家か再生工場に持ち込みます。この農ビフィルムは土で汚れているので、裁断して水洗浄します。脱水後さらに粉砕して再度水洗いし、混入している砂や金属などを除去してから、脱水・乾燥してフラフ(小片状)にします。これをさらにペレットやグラッシュ(顆粒)にします。
これは再生原料として販売されて、履物、床材や工業部品などに加工されています。
また回収された農ポリフィルムで比較的良質な物は、同様にペレットに加工されて、再生原料としてプラスチック加工業者に販売されるほか、フラワーポット・標識抗・果樹の支柱などにも加工されます。
|
 |
|
|
 |
 |